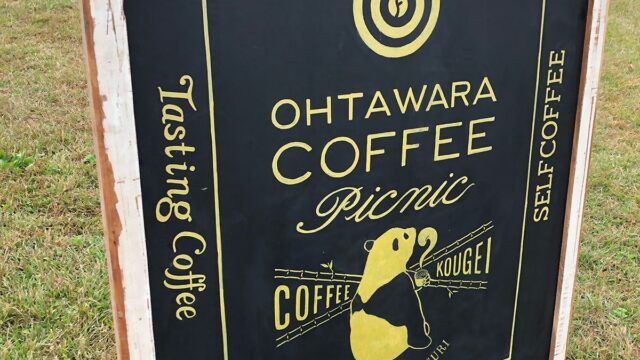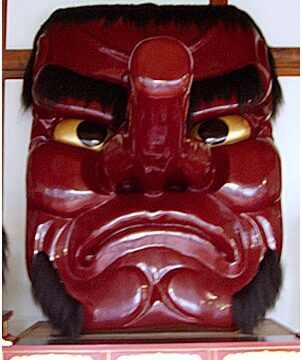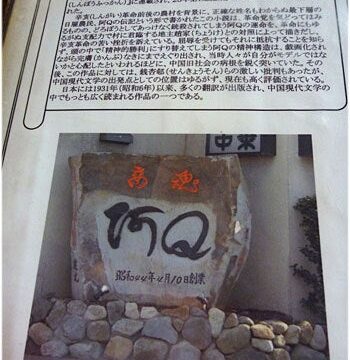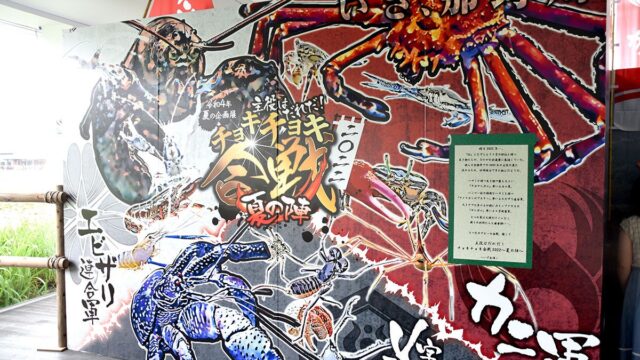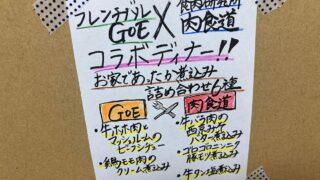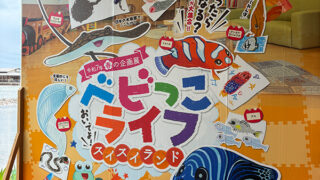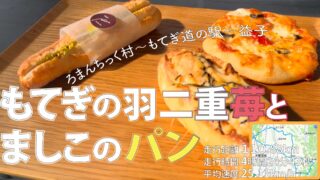スポンサーリンク
年の瀬に行った、冬の県北探訪。
よりによってめちゃくちゃ寒い日に出かけてしまいました。
場所は大田原市の湯津上地区(旧湯津上村)。

いつも車で通過してしまう古墳を、改めて鑑賞しようと、
下侍塚古墳を見に行ってきました。

国道294号の道沿いにある下侍塚古墳。
いっぱい松の木が植えられています。

冬なので「こも巻き」がされていました。
腹巻きしてるみたいでかわいい。

全景はこんな感じの「前方後方墳」。
きれいに形が残っていますね。
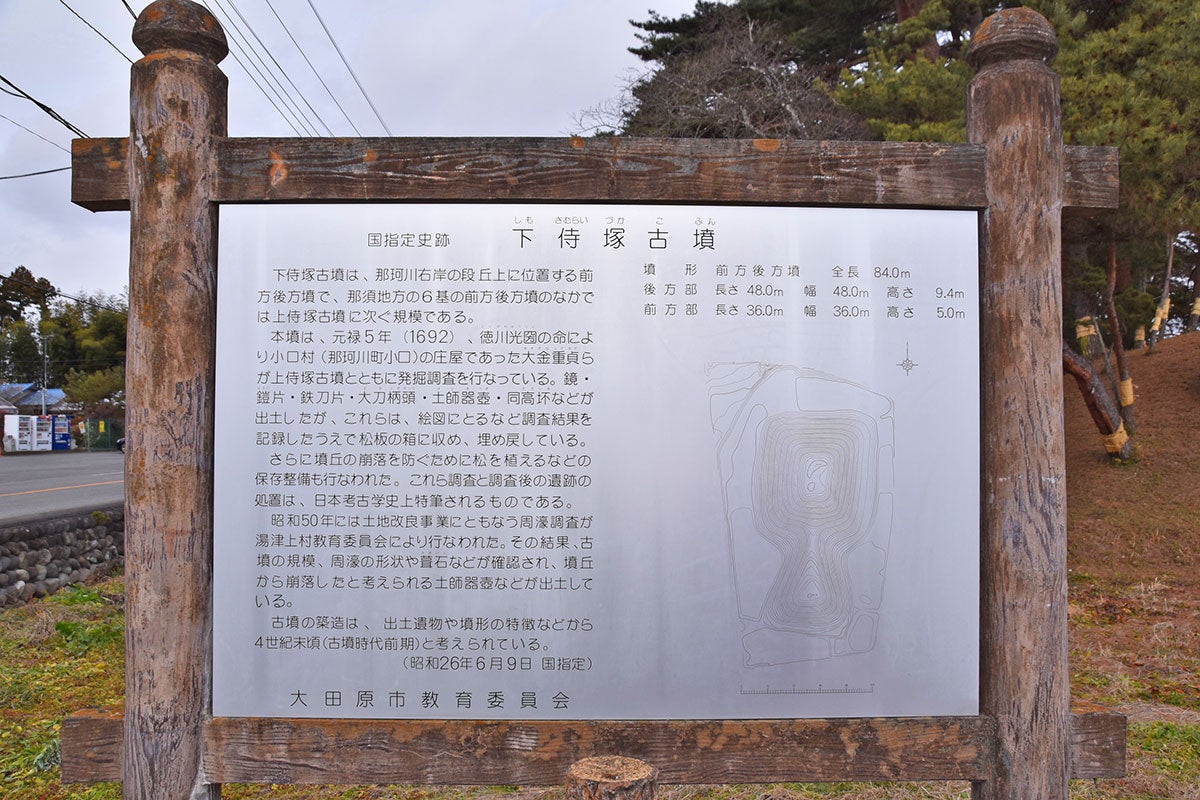
4世紀末頃(古墳時代前期)の国指定史跡の古墳です。
私も参加している「とちぎの文化財」応援団員の式でも説明されてましたが、
この古墳が、昨年(2021年)から栃木県でも重要な遺跡として
調査研究がスタートしています。
参照:

重要拠点とされている理由としては、古墳そのものの歴史もさることながら、
その後、江戸時代(元禄5年)、
この古墳発掘調査を支持したのが、「水戸黄門」こと徳川光圀で、
さらに、ここに派遣して発掘を監督していたのが、「助さん」こと佐々介三郎宗淳だから。

その調査発掘後、「この古墳を大切に保全するように」と
松を植えたのも、水戸黄門様の命だったとか。

前方後方墳のほかに、周りには方墳など全部で10基ほどがあったそうです。
(開田など開発により、現在確認できるのは8基)

この南側に、もう1つの前方後方墳の上侍塚古墳があるんですが、
寒すぎて断念・・。

古墳近くの大田原市なす風土記の丘湯津上資料館に、
詳しい資料などが展示されています。

速報展はロビーに展示されていました。
今回、2021年に行われた再調査で、詳しい測量結果なども展示されていました。
後方部の高い部分がやや窪んでいることが分かり、
もしかすると、これが水戸黄門が指示した発掘調査の痕跡かもしれない、とのこと。

水戸黄門が命じた発掘調査が、“日本で最初の学術的な発掘調査”として、
ここが「日本考古学発祥の地」として町おこしも始まっています。

茨城県の水戸黄門さんが、
なぜ栃木県のこの地で、この古墳を調べたくなったのか・・など、
今後いろいろと調査で分かってくるのでしょうか。
今後の動向にも期待ですね。
○下侍塚古墳
栃木県大田原市湯津上670
○なす風土記の丘湯津上資料館
栃木県大田原市湯津上192
【古墳の記事】
「人気ブログランキング」参加中。
↓
「いいね!」など、コメントやメッセージを
くれたりするのも更新の糧になっております。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
高根沢探訪WEBマガジン
「たかマガ」も随時更新中。
こちらもあわせてどうぞ。
↓

スポンサーリンク
スポンサーリンク